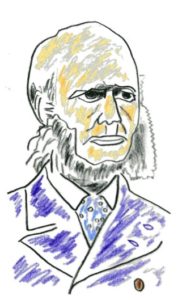その三 新政府の混乱のなかで
王政復古でご一新といっても、その過程はやたら込みいって分かりずらい。
うまれた政治権力は、堂上とはいえ下級の公家、これも今までは日の目を見ることはまずなかった下級士族、経済力を付けてきた豪商農層、国学に鼓吹された神主などが、身分差別を打ち破ろうとする民衆のエネルギーを吸い上げて敢行した日本史に例のないテロ・反乱・革命闘争から誕生したのだが、頼りがい
のある産婆は、結局、薩長の武力と外圧だった。だから、ミカド政府の中枢は武闘を指導してきた薩長の下参与たちに握られていた。
ところが、総裁・議定・参与の新三職制の宮廷順位では彼らは最下位で、御所の中でも一段下の廊下のような場所で、それぞれの藩がひと塊となって屏風で囲まれた中にたむろしていたといわれる。彼らが天皇の竜顔を拝むのは、御所庭の縁の下からだったと、宗城公はわざわざ日記に書いている。
この欺瞞体制に内心引っかかるところがあったのにちがいない。彼は大久保や、木戸と連携して宮廷改革を指向して行動している。王政復古の看板を掲げたからには、上に天皇をいただく奈良朝の古制にならって、政治の上層を担うのは公卿、その下に諸侯、本当の実力者はさらにその下というひずんだスタイルとなっていたのだ。
薩長と幕府の争いの台風の目は、「玉」としての幼沖の明治天皇だった。それを奪った者が、錦旗を掲げる権利、権力の正当性を手にする。
この論理は、江戸二百六十五年の安穏泰平のあいだに、水戸学や国学の影響下に育った新思想であるが、幕末の日本人として、宗城公の心の中にもしみこんでいたようだ。
「いろいろ問題点を指摘したが、錦旗が上がった以上は此方も新政府に協力する」
宗城公がそう宣言したので、三條初めお公家さんたちは安堵の胸をなでおろした。
どだい出来たての革命政府、さきの職制なども、朝令暮改の行き当たりばったりで、政府内権力の移動にしたがって、くるくる猫の目の様にはげしくかわった。
ミカド政府は三つの困難に直面していた。空っぽの国庫、戊辰戦争、兵庫に蝟集して圧力をかける欧米列強の艦隊と手強い外交官たち。その外交団の筆頭が辣腕英公使ハリー・パークスだった。
慶応四年一月十二日のこと、宗城公は三條実美から、
「はなはだ御苦労千万であるが、総裁宮(有栖川宮熾仁親王)や東久世も異人応対はこれまで経験がない。最初が大事なので、なにとぞお下阪なさって、よろしくお願いしたい。これは勅命でもあるので御承知ありたい」
ということになったが、勅命であるからには逃れようがない。
こうして宗城公は、同十七日に山階宮晃親王、東久世通禧ともども外國事務總督に任命され、二十二日には大坂鎮臺督も拝命した。
宗城公は外交交渉に、とりあえずは二万金が必要だろうと太政官に請求したが、返ってきた返事ではそんな余裕はない、というしまつ。
あわてた公は、寺島陶藏(松木弘安、後の外相宗則で薩藩士)、陸奥陽之助(後の外相宗光、紀州を脱藩、土佐系)、中井弘藏(田中幸介、薩藩士だが土佐系)を急遽下阪させた。大坂の豪商から資金を出させようとの魂胆である。同時に、宗城公はこの三人を太政官の参与に推薦しているのだが、実現したのは薩藩主流の寺島だけだった。
ところが、青天の霹靂。政務に寸暇の余裕もない公にとんでもない事件が起きる。
神戸事件である。